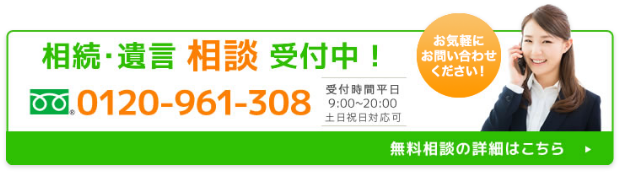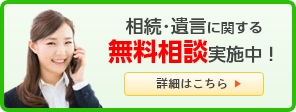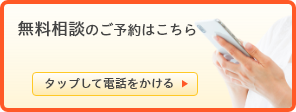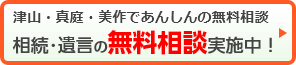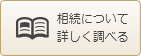2025年05月02日
Q:妻が闘病しているため、司法書士の先生に基本的な遺産相続の流れについて伺いたい。(真庭)
私は真庭に住む70代です。妻は現在闘病中で現在は入退院を繰り返しています。昔から妻に家の事を全て任せきりにしてきたツケで、妻が病気で倒れて以降は分からない事が多い中であわただしく過ぎています。そして、ついに妻の事はある程度覚悟しておくよう主治医からも伝えられました。妻は自分が闘病中にも関わらず、自分が居なくなって以降の私の心配をしている始末で、我ながら情けなく思いました。こんな事ではいけないと思い、妻がなくなった後の事も自分でしっかりと考えられるように段取りしておこうと決心しました。妻が亡くなってすぐに葬儀や相続の手続きを行わなければいけない事は分かっているので、葬儀については知人に相談をして見通しが付きました。一方の相続についても、事前に流れを把握しておきたいと思っています。お話を伺った上で、今度の事についてご相談をさせて欲しいと思っています。(真庭)
A:まずは遺産相続の基本的な流れについてご紹介します。
お忙しい中で津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせ下さり、ありがとうございます。
ご逝去後の事を考える事はとても辛い上に、遺産相続の手続きとなると理解している方は一般的に考えても非常に少ないのではないでしょうか。しかし、ご遺族が悲しみにくれるはずのご逝去後のタイミングは、実際のところやらなければならない事が山の様にあるのが現実です。気持ちに余裕をもってご家族を送れるように前もって準備しておく事は、送られる側と送る側、お互いの安心につながるのでは無いでしょうか。
まず、ご家族が亡くなって一番最初に行うべきは、遺品整理などを通じて被相続人(亡くなった方)が遺言書の遺してはいないかをご確認いただく、という事です。民法で定められた法定相続はあくまでも遺言書が無い場合のものであり、遺言書がある場合はその内容が優先されます。
今回は遺言書が無かったと仮定して、その場合の遺産相続手続きの流れを①~⑤の項目ごとにご説明いたします。
①相続人の調査
②相続財産の調査
③相続方法を決定する
④遺産分割を行う
⑤財産の名義変更を行う
①の相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集して、相続人が誰になるのかを確定します。その際に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
②の相続財産調査は、被相続人が所有していた全財産の調査を行います。財産というと現金および不動産といったプラスになる財産のみならず、借金や住宅ローンといったマイナス財産も相続の対象となります。不動産を所有している方は不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、その他銀行の通帳なども集めましょう。収集した書類をもとにして相続財産目録を作成します。
③では相続財産の相続方法を決定します。相続放棄や限定承認をするケースでは「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内」に手続きを行います。3ヶ月以内というスケジュール感はとてもタイトなので、注意が必要です。
④の遺産分割ですが、遺産相続の財産分割について相続人全員で話し合いを行う「遺産分割協議」を行います。その話し合いを通じて合意した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、そこに相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要です。
⑤では、相続した財産の名義を被相続人から相続人自身へ変更する手続きを行います。
相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野となります。まずは相続の専門家にお気軽にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では、真庭にお住いの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは一般的に考えても非常に煩雑で複雑な内容となり、多くの手間や時間がかかります。津山・岡山相続遺言相談室では真庭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧にサポートさせていただきます。地域事情に詳しい相続手続きのプロが、初回無料でご相談お伺いしております。真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、ぜひお気軽なお問合せを所員一同お待ち申し上げております。
相談事例を読む >>
2025年03月03日
Q:司法書士の先生、相続登記の申請義務化について教えてください。該当する遺産があって不安です。(真庭)
私は真庭在住の60代の主婦です。2年前に亡くなった父の遺産で気になることがあり相談しました。当時、私と妹と弟の3人が相続人でしたので遺産分割協議を行って、かなり時間はかかりましたがとりあえずまとまりました。その後、しばらくして父名義の不動産が見つかったのですが、正直あの面倒な作業をまたやらなければならないことと、相続人である妹と弟が忙しくて日が合わなかったこともあって、その土地は現在も放置されています。先日、相続登記の話をテレビで見てあの土地はどうなるんだろうと疑問に思いました。父が亡くなったのは2年前ですので、関係ないとは思いましたが、念のため相続登記の義務化について簡単に教えてください。(真庭)
A 2024年4月1日に施行された相続登記の義務化ですが、施行前の相続も義務化の対象です。
まず、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(相続登記)が義務化された背景ですが、期限のなかった従来では、故人名義のまま変更されず、その後の所有者が不明のまま放置される不動産が多々あり、放置された不動産が増えたことで老朽化した建物の倒壊や、景観が損なわれたりと近隣住民に迷惑がかかるだけでなく犯罪自体も増加しました。このような背景から相続登記の申請が義務化されることとなりました。
相続登記の申請義務化が施行され「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。
この法改正では、施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。「相続による所有権の取得を知った日」ないし「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられてはいますが、対象の方で相続登記をしていない方は津山・岡山相続遺言相談室まで早急にご連絡ください。初回のご相談は無料で行っております。
なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまっていない場合には、法務局で「相続人申告登記」を行ってくことで、所有者が明らかにされるため、期限内に相続登記ができなくても過料の対象から外れます。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にお任せください。真庭をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている津山・岡山相続遺言相談室の専門家が、真庭の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
相談事例を読む >>
2024年12月03日
Q:私には離婚歴があるのですが、私の財産を相続するのが誰になるのか、司法書士の方にお尋ねします。(真庭)
私は真庭在住の70代男性です。終活について考えた時に、私の財産を相続する人はいったい誰になるのか疑問に思い、ご連絡させていただきました。
私には離婚歴があります。前妻との間に子供はおりません。前妻は現在真庭から遠く離れたところで暮らしているので、私の訃報が前妻にまで伝わることはないとは思うのですが、私の財産を前妻が相続する可能性はあるのでしょうか?
実は私にはいま真庭で同居している、いわゆる内縁の妻がおりますので、私の財産は内縁の妻にすべて渡したいと思っています。内縁の妻に財産を渡すことはできるのか、そもそも相続人は誰になるのか、教えていただけますか。(真庭)
A:法律婚の配偶者は相続人となりますが、離婚した前妻や事実婚の方は相続人とはなりません。
まず、前妻の方と離婚が成立しているのであれば、前妻の方が相続人となることはありません。また、法律婚の配偶者でなければ相続人になることはできないため、事実婚の状態である内縁の奥様も相続人にはなれません。
民法では、法定相続人(法的に相続権を有する人)を以下のように定めています。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:直系卑属である子(孫)
- 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
- 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹
※法律婚の配偶者は常に法定相続人です。次に第一順位の人が相続人となりますが、該当者がいない場合には第二順位に相続権が移ります。上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の人は相続人とはなりません。
真庭のご相談者様に、上記に該当する方がいる場合、その方が相続人となります。もし誰もいなければ、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用し、真庭でご同居の内縁の奥様が財産の一部を取得できる可能性もあります。この制度は、内縁の奥様が、ご相談者様の逝去後に家庭裁判所へ申立てを行い、特別縁故者として認められる必要があります。特別縁故者に認められない場合、財産は取得できません。
内縁の奥様に確実に財産を渡したいのであれば、生前のうちに遺言書を作成しておく方法があります。内縁の奥様に財産を遺贈(遺言を通して相続人以外の第三者に財産を渡すこと)する旨を記載しておきましょう。より遺言の確実性が高い「公正証書遺言」という遺言方法で遺言書を作成しておくと安心です。
津山・岡山相続遺言相談室は相続・遺言の専門家として、真庭の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう、家族のように寄り添いお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は完全無料ですので、真庭の皆様はぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。
相談事例を読む >>